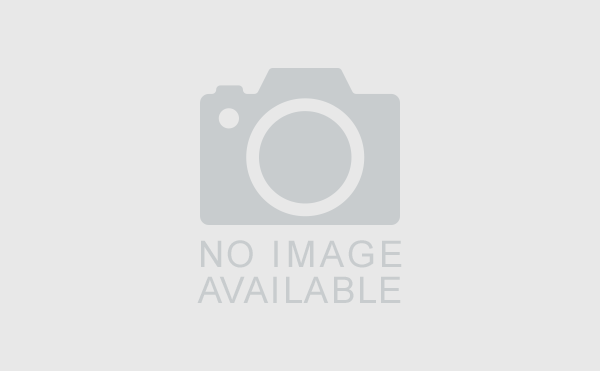産休・育休・時短勤務利用者のフォローをめぐる調査研究
産休・育休・時短勤務利用者のフォローをめぐる調査研究
昨年度より、NPO法人あざれあ交流会議の令和6・7年度調査研究事業「職場における産休・育休・時短勤務利用者に対するフォロー従業員の意識調査」の監修を担当させていただいている。同調査は、昨今に男性の育児休業取得率が高まっていることを受けて、産前産後休暇・育児休業・短時間勤務制度(以下、産休・育休・時短勤務)の利用者の業務をフォローしている従業員がどのような課題を抱えているのかを把握しようとするものである。
この調査では、産休・育休・時短勤務のフォローを「産休・育休・時短勤務等を利用している従業員の業務を代わりに行うこと(あるいは、ある職場の従業員が産休・育休・時短勤務等を利用したことによって生じた業務を行うこと)」と定義している。同調査には、同休暇・休業の制度の利用者だけでなく、その利用者の周囲の人たちにとっても利益がもたらされる、あるいは、配慮が行き届くようにする環境をつくりだす取り組みに向けた基礎資料を提供することが期待されていると考えている。
「昨今に男性の育児休業取得率が高まっていることを受けて」と先述したが、産休・育休・時短勤務のフォローは、最近になって課題となったことではないようである。例えば、「育児休業 フォロー」と入力してウェブ検索をしてみると、多くはこの1、2年の間の記事が挙がってくるが、その中には、2018年や2011年の記事もある。現在になって注目されつつある出来事が、これまでにも起きていたことに気づかされる。
記事の内容を見てみると、フォローをしていて自分自身が疲労してきた、という経験や出来事がフォロー者の方々の視点から記されていることが印象的である。フォローを必要としている人々の支援を考えながら、フォローをしている人々の支援も考える、ということが求められているように思える。難題であるが、今回監修を担当させていただいている調査研究によって明らかとなった知見が、少しずつでもその課題の解決に寄与してくれたらと願うと同時に、そうなるように努力したいと考えている。
(滑田明暢 大学教育センター)