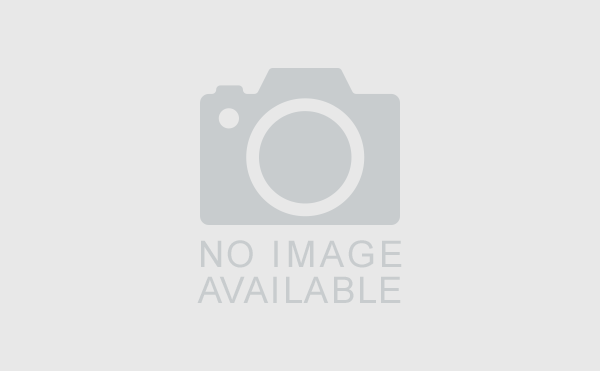新任教員自己紹介:鵜飼峻二
2025年4月より静岡大学教職センターの特任助教として着任いたしました鵜飼峻二です。専門はアメリカ哲学で、これまで、主にジョン・デューイの教育哲学を西洋哲学史(特に形而上学と宗教)の視点から検討する解釈学的研究に取り組んできました。自己紹介のために、哲学研究に関心を持つようになった経緯を振り返りたいと思います。
原体験は3つあります。1つ目は、幼少期から小学校卒業まで、10年間、アメリカ・カリフォルニア州で過ごしてから、日本の主に学校教育への適応を試みた経験です。特に目立った言動をしたわけではないにもかかわらず、いわゆる「帰国子女」として扱われ、日本であるべき姿に関する助言をされるなど、日本への同化を暗に促されるような経験が印象に残っております。こうした経験を避けるべく私は帰国子女であることを隠すようになり、その結果として、担任の先生から「英語、喋れるの?」と尋ねられるほどに、日本でのいわゆる「普通」の生活に馴染むようになりました。
2つ目の原体験は、上述の経験とは真逆のものでした。一度は東京で大学生となったものの、交換留学先のアメリカ・アイオワ州グリンネル大学のリベラルアーツ教育に強く惹かれ、最終的に同大学に編入学しました。アイオワ州の片田舎にある、学生数2000人未満の全寮制大学という静かな環境の中で、多様な背景を持つ学生たちが高密度な学びを展開している様子に直面したとき、「ここで教育を受ければ人生が変わるかもしれない」と真剣に思ったのです。編入後は、主に人類学・哲学・教育学・音楽の4分野を集中的に学び、最終的に人類学を専攻しました。また、学問的関心を深める傍らで、留学生受け入れの補助、日本語教育ボランティア、合唱団での全米縦断ツアーへの参加、ラテン・アメリカ音楽アンサンブルでの演奏、ダイニングホールの前でのゲリラ打楽器ライブの企画、東日本大震災のチャリティ・イベントの開催など、さまざまな活動に精力的に取り組みました。
これが1つ目の原体験となぜ「逆」かと言えば、グリンネル大学での学びでは、「適応」よりも、既存の考え方や現状を批判的に検証し、より広く深い知見を探求する姿勢が積極的に推奨されていたと感じたからです。編入学のために書いた申請書に、19世紀のアメリカの著述家ヘンリー・D・ソローの『ウォールデン』から、次の一節を引用したのを今でもよく覚えています。
「地球の表面は、人の足に敏感に応じます。同じように、人の心の旅も、後に道を残します。いったい、世界の人の心の街道は、どれほど使い古され、埃まみれであるでしょう!人々の心の旅路に、因習と同化の轍の窪みが、どれほど深く刻まれているでしょう!私は船に乗るなら、客室ではなくマストの前で、地球のデッキで、すべてが見えるところで、昼夜を過ごしたいと願ってきました。そこから私は、月の美しい光に照らされた山々を見ました。今の私は、デッキの下の豪華な一等船室に降りる気はありません」(H・D・ソロー(2016)『ウォールデン 森の生活 下』今泉吉晴訳、小学館、397-398頁)。
グリンネル大学での経験は、まさに当時の私にとって、「因習と同化の轍」をなぞることから離れ、「マストの前」に立ち、広い世界を見ようとする新たな姿勢を教えてくれるものでした。
3つ目の原体験は、哲学を専攻する決意を固めたことです。留学を終えた後、私は教育学を専攻し、名古屋で大学院生活を始めました。修士課程では、デューイ研究を行うことにしました。名古屋での生活は、主に、デューイ哲学に没頭して彼の思索的格闘を追体験することで、現代に通ずるさまざまな考え方や課題を発見する時間となりました。たとえば、自然科学や社会科学の成果は、どのように西洋の伝統的な思想や価値観に挑戦し、また新たな価値観を創造することに寄与するのか。多文化主義や民主主義の現代的意義とは何だろうか。複雑化する社会において、自由な学びや探究を行うとはどういうことなのか。こうした問題圏を発見する航路を辿りつつ、私は、大学院生向けの学際的な学内プログラムに参加するなどして、グリンネル大学在学時と同様、非常に活動的な大学院生活を送りました。
しかし、研究を進める中で、私が関心を寄せる問いの群が哲学的な性質を持っていることに気づくとともに、教育学部の同僚たちが、必ずしもそれらを研究の題材として取り上げることに関心を寄せていないことを知りました。そして、それらの問いに関して深く掘り下げて探求を行うためには、西洋哲学史に関する本格的な理解が不可欠であると痛感するようにもなりました。そのような問題意識のもと、私は名古屋の大学院を中退し、オレゴン大学へ大学院留学することにしました。専攻は哲学です。
オレゴン大学では、それまでの活動的な大学院生活とは一転し、西洋哲学史の精読に徹する日々を送りました。コースワークで哲学史の古典を読み解き、また友人たちと、自主的な輪読会を毎日のように開催しました。たとえば、ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーの哲学史講義を一冊また一冊と読み進めたり、オランダの哲学者バルーフ・スピノザの名著『エチカ』を一文ずつ音読しながらその意味を考察したりと、地道ながらも充実した時間を重ねました。こうして西洋哲学史に真剣に取り組む中で、私がかつて強く魅了されたアメリカのリベラルアーツ教育や、デューイ主義的な理論と教育実践が、実は西洋哲学の深い水脈の中から育まれたものであることを理解するようにもなりました。
しかし、オレゴン大学での5年間の留学経験は、学問的追求の充実とは裏腹に、自由な学びを脅かすような現実と直面する時間にもなりました。激しい政治的対立や偏見に起因する暴力への恐怖、過剰な美徳シグナリングとそれに付随する偽善、さらにはシニシズムなど、学びの場を覆うさまざまな緊張感を、肌でヒリヒリと感じながら、哲学史の読解へと日々向き直っていました。多様性や自由が尊ばれる一方で、それがかえって折衷不可能に見える対立を生み出すこともある。また、そのような対立を避けるために、人々が退避的・消極的になってしまうこともある――こうした現実を、私は身をもって学ぶことになったのです。
1947年、デューイは「哲学の未来」と題するコロンビア大学での講演において、全体主義に対する強い危機感を表明し、それに対抗する手段として、民主主義の継続的な意義を強調しました。デューイにとっての全体主義とは、異質なものを積極的に排除する文化のことであり、それは激しい偏見や排他主義などによって強化されるとされます。こうした傾向性に対抗する一手段として、デューイは、自由なものの考え方を促進する哲学の役割を重視しました。他方で、戦後の英米圏における主流の哲学的動向を見渡し、彼は失望を表明しています。正しい選択が一体何なのかが見えにくい時代にあって、自由な発想を許容し、それを具体的な探究へと結びつけられるものの考え方とは、一体、どのようなものだろうか。このような問いに対する答えを模索する試みは、21世紀においても尚重要であり、むしろ、意義が高まっているように思います。
静岡大学においては、教師を目指す学生の皆さんと共に、こうした問いに真摯に向き合いながら、柔軟かつ深い思索を育むことができる対話の場を築いていけたらと考えています。